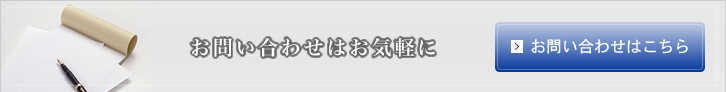日米交歓ディベート
国際交流局は、日米交歓ディベートツアーをとり行うための業務を担当しています。隔年ごとに代表ディベーターを派遣しあい、双方の国で各地の大学、ディベート団体、ディベート大会等を歴訪し、公開ディベートやコーチによる講演を行うことで、ディベートにおける交流促進と草の根レベルの国際交流を図っています。日程は例年若干異なりますが、標準的には2月末から3月にかけて日本から代表ディベーターを米国へ送り、翌年6月に米国からの代表ディベーター(2名)およびコーチ(大学教授など、1名)が日本を訪問します。
日米交歓ディベートは、JDA発足以前から元JDA副会長の故スコット・ハウエル神父(元上智大学理学部教授、上智短期大学副学長)を中心にJapan English Forensic Associationが日本側の受け入れ団体としてSpeech Communication Association(アメリカ・スピーチコミュニケーション学会)との共催で実施されており、その歴史は既に約50年にわたります。現在は、JDAとNational Communication Association(全米コミュニケーション学会)のCommittee on International Discussion and Debate(国際ディスカッション・ディベート委員会)との共催で開催しています。
2023年日米交歓ディベート 全米代表 日本ツアー
開催要項
米国代表コーチ
Kenneth Newby (Morehouse College) &
John Koch (Vanderbilt University)
米国代表ディベーター
Daniel E. Ardity (Vanderbilt University)
Nine Abad (University of Houston)
| 主催 | 日本ディベート協会 (Japan Debate Association) | |
|---|---|---|
| 協力 | 米国コミュニケーション学会 国際ディスカッション・ディベート委員会 (Committee on International Discussion and Debate, National Communication Association) |
|
| 開催期間 | 2023年6月13日(火)~6月21日(水) | |
| ツアー日程 | 6/13 (火) | 来日 |
| 6/14 (水) | 九州大学 | |
| 6/15 (木) | 桃山学院大学 | |
| 6/17 (土) | 日本社会人ディベート連盟(JBDF) | |
| 6/18 (日) | 全国英語ディベート連盟(HEnDA) | |
| 6/19 (月) | 日本ディベート協会 | |
| 6/21 (水) | 離日 | |
2021年日米交歓ディベート 全米代表 日本ツアー
開催要項
日本ディベート協会では、各年ごとにアメリカ合衆国とお互いにディベート・チームを送りあい、議論教育の発展と国際交流に寄与してきました。しかしながら、今回は新型コロナウイルスの影響で物理的にツアーを開催することが不可能になりました。
そこで、2021年6月は、オンラインで以下の試合を執り行うことといたします。詳細は以下のとおりです。
米国代表ディベーター
John Huebler (University of Mary Washington卒)
Emma Reilly (Randolph-Macon College)
試合
2021年6月5日(土)9:00AM 対 日本社会人ディベート連盟(JBDF)代表 戦
Resolved: That the Japanese government should introduce a carbon tax.
Affirmative: JBDF Team vs. Negative: Team USA
全米チームコーチ: John P. Koch, Ph.D (Vanderbilt University)

動画アーカイブは、こちらからご覧ください。
2021年6月19日(土)9:00AM 対 全国英語ディベート連盟(HEnDA)代表 昨年度全国大会優勝校 市立浦和高校チーム 戦
Resolved: That the Japanese Government should relocate the capital functions out of Tokyo.
全米チームコーチ: Ruth J. Beerman, Ph.D (Randolph-Macon College)
動画アーカイブは、こちらからご覧ください。
2021年6月26日(土) 対 パーラメンタリー・ディベート代表 戦
Motion: This House would ban the ownership of firearms.
日本代表:Rina Kajitaniさん(東京大学)、Kim Senaさん(University of Pennsylvania今秋入学予定)
全米チームコーチ:Kenneth Newby, J.D. (Morehouse College)
動画アーカイブはこちらをご覧ください。
2020年日米交歓ディベート 日本代表 全米ツアー
開催要項
| 主催 | 日本ディベート協会 (Japan Debate Association) | |
|---|---|---|
| 協力 | 米国コミュニケーション学会 国際ディスカッション・ディベート委員会 (Committee on International Discussion and Debate, National Communication Association) |
|
| 開催期間 | 2020年2月23日~3月17日 | |
| 日本代表 | ディベーター | Yuta Watanabe (Waseda University)
Takuto Kasahara (Kanazawa University) |
| ツアー日程 | 2/23-2/25 | Wheaton College |
| 2/25-2/27 | Duquesne University | |
| 2/27-2/29 | Slippery Rock University | |
| 2/29-3/2 | University of Georgia | |
| 3/4-3/6 | Baylor University | |
| 3/6-3/8 | University of Southern Mississippi | |
| 3/8-3/10 | University of Denver | |
| 3/10-3/12 | Pierce College | |
| 3/12-3/14 | CSU-Northridge | |
| 3/14-3/17 | University of Utah | |
2019年日米交歓ディベート 全米代表 日本ツアー
開催要項
| 主催 | 日本ディベート協会 (Japan Debate Association) | |
|---|---|---|
| 特別協賛 | GTEC | |
| 協力 | 米国コミュニケーション学会 国際ディスカッション・ディベート委員会 (Committee on International Discussion and Debate, National Communication Association) 全国高校英語ディベート連盟 (All Japan High School English Debate Association) |
|
| 開催期間 | 2019年6月4日(火)~6月25日(火) | |
| 全米代表 チーム |
コーチ | Dr. Ruth J. Beerman (Ms.)
ランドルフ・メイコン大学(Randolph-Macon College)
コミュニケーション学部 助教授、ディベート・スピーチ部 監督(Assistant Professor of Communication Studies, Co-Director of Debate and Forensics)、博士(Ph.D)
|
| ディベーター |
Colten White, University of Nebraska-Lincoln(
Caroline Kouneski, Randolph-Macon College(ランドルフ・メイコン大学 卒)
|
|
| ツアー日程 | 6/4 (火) | 来日 |
| 6/5 (水) | ガイダンス/歓迎会(申し込みはこちらから) | |
| 6/6 (木) | 神田外語大学 グローバルコミュニケーション研究所 | |
| 6/7 (金) | 東海大学 文学部英語文化コミュニケーション学科 | |
| 6/8 (土) | 岐阜聖徳学園高等学校、HEnDA岐阜支部 | |
| 6/9 (日) | 日本コミュニケーション学会 | |
| 6/10 (月) | 福井県高等学校教育研究会英語部会 | |
| 6/11 (火) | 立命館大学 言語教育センター | |
| 6/13 (木) | 宮崎県高等学校教育研究会英語部会 県高校英語ディベート研究部 | |
| 6/14 (日) | JDA九州支部、九州大学言語文化研究院、福岡県立城南高等学校(予定) | |
| 6/15-16 (土-日) | 広島修道大学 学習支援センター | |
| 6/18 (木) | 鹿児島高文連 国際交流専門部 | |
| 6/19-20 (水-木) | 北海道高等学校文化連盟国際交流専門部、北海道札幌国際情報高等学校 | |
| 6/22 (土) | 群馬県高等学校教育研究会英語部会 | |
| 6/23 (日) | 日本社会人ディベート連盟(JBDF) | |
| 6/24 (月) | 送別会 | |
| 6/25(火) | 離日 | |
2019年6月9日 (日)ディベートマッチとサポート資料公開
この度、日本コミュニケーション学会で6/9(日)に開催いただいたイベントの日米交歓ディベート・マッチを公開できる運びとなりました。また、日本チームが作成した準備資料もあわせて公開いたします。
これもひとえに、ご参加いただいた方々と主催団体のご厚意によるものです。米国チームの三人(Ruth Beerman博士、Colten Whiteさん、Caroline Kouneskiさん)、日本チームの佐藤可奈留さんと樋口拓也さんには、あらためて厚く御礼申し上げます。また、この会場を提供いただき、録画を許可していただき、活発なディスカッションを可能にしてくれた日本コミュニケーション学会(http://www.caj1971.com/)、ならびにツアー全体の特別協賛をいただいたGTEC(https://www.benesse.co.jp/gtec/)にも厚く御礼申し上げます。
この動画の使用については、私用目的と教育目的(高校生・大学生向け)に限ります。セミナーなどの商用目的での使用や動画販売については、ツアーの目的、上記の方々の意図、そしてこの機会をご提供いただく各団体の意図に反するため、これを固く禁じます。
なお、マテリアルについてはほとんど全てを英語のものからとっているため、misrepresentation/distortionの心配はほぼないと思われます。日本語のものについては、各自購入の上お確かめいただけますと幸いです。
また、このイベントはHEnDA(http://henda.global/)の論題を採用しております。ただし、HEnDAルールに準ずるのはフォーマット(各スピーチの順番と時間)のみであったことを改めてご確認いただけましたらと思います。
以上をご確認のうえ、議論教育とディベートの普及に大いに役立てていただけましたら幸いに存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
なお、こちらのページでツアー全体と、近況をご覧いただけます。
https://japan-debate-association.org/en/seminar/exchange
https://www.facebook.com/CIDDtours/
https://www.facebook.com/japan.debate/
00 format https://youtu.be/tQtU4S-t940
01 introduction & AC https://youtu.be/0VmrLCcnDUU
02 Japanese comments https://youtu.be/z3FJwXpXJDM
03 CX https://youtu.be/Otf02bvNfeg
04 NC https://youtu.be/ysQwz4jDFDU
05 Japanese comments https://youtu.be/wp-sTHDN06M
06 CX https://youtu.be/M3QfjzWe-Oo
07 NA https://youtu.be/br2u7NO2Ayw
08 CX https://youtu.be/AJjWi4VSMr8
09 AA https://youtu.be/HxpPOREh-YQ
10 CX https://youtu.be/Zdh_GTjrJfQ
11 AD https://youtu.be/tVf1ovCKd6I
12 ND https://youtu.be/BsPj8dI10Jw
13 AS https://youtu.be/5qztw7FY92o
14 NS https://youtu.be/ELbelvU9jF0
15 post-round comments and questions from the audience https://youtu.be/-m-BTpivi_c
Files used by Japan Team (productivity, politics DA, & social movement Kritik) are available at: http://bit.ly/2ZiiDCw
開催要項
| 主催 | 日本ディベート協会 (Japan Debate Association) | |
|---|---|---|
| 協力 | 米国コミュニケーション学会 国際ディスカッション・ディベート委員会 (Committee on International Discussion and Debate, National Communication Association) |
|
| 開催期間 | 2018年2月23日~3月9日 | |
| 日本代表 | ディベーター | Kanaru Sato (University of Tokyo)
Takuya Higuchi (Rikkyo University) |
| ツアー日程 | 2/23-2/25 | Weber State University |
| 2/25-2/27 | Randolph-Macon College | |
| 2/27-3/1 | Duquesne University | |
| 3/1-3/3 | University of Southern Mississippi | |
| 3/3-3/5 | Howard Payne University | |
| 3/5-3/7 | University of Southern California | |
| 3/7-3/9 | California State University, Northridge | |
2017年日米交歓ディベート 全米代表 日本ツアー
開催要項
| 主催 | 日本ディベート協会 (Japan Debate Association) | |
|---|---|---|
| 特別協賛 | GTEC | |
| 協力 | 米国コミュニケーション学会 国際ディスカッション・ディベート委員会 (Committee on International Discussion and Debate, National Communication Association) 全国高校英語ディベート連盟 (All Japan High School English Debate Association) |
|
| 開催期間 | 2017年6月6日(火)~6月27日(火) | |
| 全米代表 チーム |
コーチ | Dr. John M. Kephart III (Ph.D.)
カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 コミュニケーション学部 准教授 ディベート・スピーチ部監督 |
| ディベーター | Elijah Smith, Wake Forest University ウェイク・フォレスト大学 Allison Foust, Regis University レジス大学 |
|
| ツアー日程 | 6/6 (火) | 到着 |
| 6/7 (水) | ガイダンス/歓迎会 | |
| 6/8 (木) | 神田外語大学 グローバルコミュニケーション研究所 | |
| 6/9 (金) | 東海大学 文学部英語文化コミュニケーション学科 | |
| 6/11 (日) | 広島修道大学 学習支援センター | |
| 6/13 (火) | JDA九州支部、九州大学言語文化研究院 | |
| 6/14 (水) | 愛媛大学ESS | |
| 6/15 (木) | 宮崎県高等学校教育研究会英語部会 | |
| 6/17 (土) | 福井県教育委員会 | |
| 6/18 (日) | 近江兄弟社高等学校 | |
| 6/20 (火) | 茨城県高等学校教育研究会英語部 | |
| 6/22-23 (木-金) | 北海道高等学校文化連盟国際交流専門部、北海道札幌国際情報高等学校 | |
| 6/24 (土) | 埼玉県高等学校英語教育研究会 | |
| 6/25 (日) | 日本社会人ディベート連盟(JBDF) | |
| 6/26 (月) | 送別会 | |
| 6/27(火) | 離日 | |
2016年日米交歓ディベート 日本代表 全米ツアー
開催要項
| 主催 | 日本ディベート協会 (Japan Debate Association) | |
|---|---|---|
| 協力 | 米国コミュニケーション学会 国際ディスカッション・ディベート委員会 (Committee on International Discussion and Debate, National Communication Association) |
|
| 開催期間 | 2016年2月20日(土)~3月10日(木) | |
| 日本代表 | ディベーター | Naruhiko Nakano (Mie University E.S.S.) |
| ツアー日程 | 2/20-2/23 | Irvine Valley College |
| 2/23-2/26 | Texas Christian University | |
| 2/26-2/29 | University of Rhode Island | |
| 2/29-3/2 | Samford University | |
| 3/2-3/4 | University of Utah | |
| 3/4-3/7 | George Washington University | |
| 3/7-3/8 | CSU Northridge | |
| 3/8-3/9 | Loyola Marymount University | |
| 3/9-3/10 | Santa Monica College | |
2015年日米交歓ディベート 全米代表日本ツアー
開催要項
※訪問スケジュールの詳細は、英語ページの旅程(itinerary)をご参照下さい。
| 主催 | 日本ディベート協会 (Japan Debate Association) | |
|---|---|---|
| 特別協賛 | GTEC CBT | |
| 協力 | 米国コミュニケーション学会 国際ディスカッション・ディベート委員会 (Committee on International Discussion and Debate, National Communication Association)全国高校英語ディベート連盟 (All Japan High School English Debate Association) |
|
| 開催期間 | 2015年6月2日(火)~6月23日(火) | |
| 全米代表 チーム |
コーチ | Dr. Theodore F. Sheckels, Jr.
ランドルフ・メイコン大学教授 |
| ディベーター | Natalie Bennie サムフォード大学 (Samford University)Cody Walizer デンバー大学 (University of Denver) |
|
| ツアー日程 (旅程詳細) |
6/2(火) | 到着 |
| 6/3(水) | ガイダンス/歓迎会 | |
| 6/5(金) | 神田外語大学 グローバルコミュニケーション研究所 | |
| 6/6(土) | 日本社会人ディベート連盟(JBDF) | |
| 6/7(日) | 東京学生ディベート連盟(TIDL) | |
| 6/8(月) | 北海道高等学校文化連盟国際交流専門部 | |
| 6/10(水) | 鹿児島県高等学校教育研究会英語部会ディベート専門部 | |
| 6/11(木) | JDA九州支部、九州大学言語文化研究院 | |
| 6/12(金) | 福岡県高等学校英語教育研究部会 /福岡県修猷館高等学校 |
|
| 6/13(土) | 愛媛大学ESS | |
| 6/14(日) | 全国高校英語ディベート連盟岐阜支部 | |
| 6/16(火) | 慶應義塾大学 | |
| 6/17(水) | 愛知淑徳大学交流文化学部 | |
| 6/18(木) | 茨城県高等学校教育研究部会英語ディベート委員会 | |
| 6/20(土) | 栃木県高文連英語部会 | |
| 6/21(日) | 全日本英語討論協会(NAFA) | |
| 6/22(月) | 送別会 | |
| 6/23(火) | 離日 | |
過去の開催情報
| 開催年 | 報告 | 日程 | 開催国 | 来訪・訪問者 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3月2日〜3月27日 | 米国 |
|
|
| 2013 | 6月4日〜6月24日 | 日本 |
|
|
| 2012 | 6月4日〜6月24日 | 日本 |
|
|
| 2011 | 2月20日〜3月17日 | 米国 |
|
|
| 2010 | 未開催 | |||
| 2009 | 6月4日〜6月24日 | 日本 |
|
|
| 2008 | 2月24日〜3月21日 | 米国 |
|
|
| 2007 | 6月7日〜6月27日 | 日本 |
|
|
| 2006 | 2月11日〜3月18日 | 米国 |
|
|
| 2005 | 日本 |
|
||
| 2004 | 2月28日〜4月4日 | 米国 |
|
|
| 2003 | 6月13日〜7月1日 | 日本 |
|
|
| 2002 | 未開催 | |||
| 2001 | 6月11日〜7月2日 | 日本 |
|
|
| 2000 | 2月17日〜3月29日 | 米国 |
|
|
| 1999 | 6月10日〜6月27日 | 日本 |
|
|
| 1998 | 2月16日〜3月26日 | 米国 |
|
|
| 1997 | 6月12日〜7月8日 | 日本 |
|
|
| 1996 | 英語 | 2月24日〜4月2日 | 米国 |
|
| 1995 | 日本 |
|
||
| 1994 | 米国 |
|
||
| 1993 | 日本 |
|
||
| 1992 | 米国 |
|
||
| 1991 | 日本 |
|
||
| 1990 | 米国 |
|
||
| 1989 | 日本 |
|
||
| 1988 | 米国 |
|
||
| 1987 | 日本 |
|
||
| 1986 | 米国 |
|
||
| 1978 | 2月〜3月 | 米国 |
|

 English
English