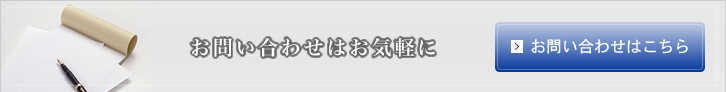2024年「ディベーター(ディベート)・オブ・ザ・イヤー」 決定のお知らせ
特定非営利活動法人日本ディベート協会(Japan Debate Association (JDA))は、「ディベート(議論)とはかくあるべし」というモデルを日本でディベートを学ぶ人たちのために提示し啓発するべく、「ディベーター(ディベート)・オブ・ザ・イヤー(Debate(r) of the Year (DOTY))」賞を毎年選出しております。
この度、JDAは、小手鞠るい『ある晴れた夏の朝』(小説およびそれを原作とした舞台)を2024年DOTYに選出いたしました。https://www.atpress.ne.jp/news/428833
受賞理由は以下の通りです。
小手鞠るい氏の小説『ある晴れた夏の朝』は、アメリカの高校生が、日本への原爆投下の是非をめぐりディベートする物語です。本作が出版されたのは2018年ですが、2024年に文庫版が出版されました。また舞台化もされ、2024年には作者の故郷であり広島に隣接する岡山で上映されました。
本作には、米国で暮らす日本人という筆者の経験を活かし、原爆投下を肯定する米国的な立場と、否定する日本的な立場の両方が登場します。本作は英語版も出版されたため、日本へは日本の人々が知らなかった米国の意見を、米国へは米国の人々が知らなかった日本の意見を、届けることに成功しています。
本作が伝えるのは、原爆に関する議論だけではありません。小手鞠氏はインタビューで、「話し合うことの大切さ、意見を交わし合うことから見えてくる何かがあるということを、日本の読者に伝えたいと思いました。これが本書の隠れた狙いです。」と述べています。とくに、「子どもも大人も、です。上司と部下であっても、議論の場では対等。(……)たとえ猛烈な反論を展開しても、それが終わればハグをして別れる…みたいな感じで、友情は壊れません。というようなことが、日本の読者に伝わったらいいなーと思っておりました。」等の発言からは、ディベートの大前提である、立場の対等性や議論と人格の分離といったポイントの周知への貢献がうかがえます(*)。
以上のことから、「日本における『より良き』ディベート活動の普及への貢献」を設立当時から基本理念に掲げるJDAが選定するDOTY受賞に値すると判断しました。また、戦後80周年を迎える2025年の春に報告される運びとなる、本第4回DOTYに相応しいと考えました。
(*) 小林章子(2024)「『原爆肯定派? 否定派?』高校生が“原爆の是非”をディベートする物語 作家・小手鞠るいさんの『ある晴れた夏の朝』 舞台上演も」https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rsk/1221687?display=1
受賞をうけまして、小手鞠るい様よりコメントをいただきました。
このたびは、栄えある賞をお贈りくださって、ありがとうございます。
2024年「ディベート/ディベーター・オブ・ザ・イヤー(DOTY)」の受賞を、『ある晴れた夏の朝』で討論をくり広げてくれた、アメリカ人の高校生8人と共に、そして、本作を出版してくださった偕成社のみなさま、文庫化してくださった文藝春秋のみなさまといっしょに、喜びたいと思います。
この作品は、子どもから大人まで、戦争を生き抜いてきた世代から、戦争を知らない世代まで、実に幅広い読者の方々に読まれ、支持されてきました。
その理由のひとつは「広島と長崎への原爆投下の是非」という、途方もなく難しく、重いテーマに対して、ありとあらゆる資料を調べ、果敢に意見を述べ合った高校生たち8人のガッツにあったと思っています。彼ら、彼女たちは天晴れでした。思考を停止させたり、表現を美化したり、結論を一般化したりすることなく、あくまでも一個人として、わたしは、ぼくは、こう思う、と主張し、反対意見を述べるときにも臆さず、しかし、礼を尽くして語り合う。討論が終わったら、笑顔でハグをし合う。そんな姿勢の中からこそ、机上の空論には終わらない、平和の創造が可能になってくるのではないか。わたしも、この8人から、話し合うことの大切さを学ばせてもらったひとりであった、と思っています。
小手鞠るい
お忙しいなか、受賞コメントをいただきありがとうございます。

 English
English